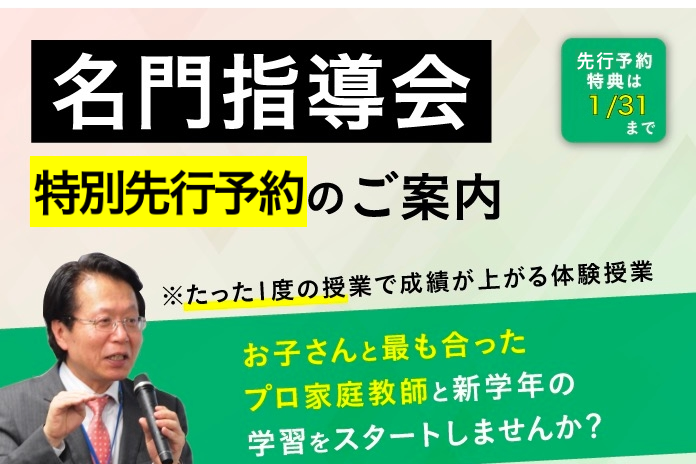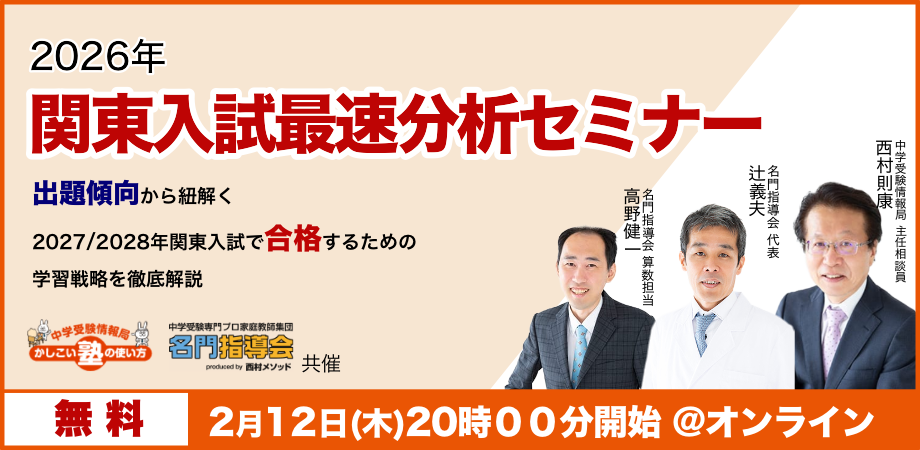カテゴリー: 未分類 Page 8 of 22
夏休みですね。
6年生は「受験の天王山」と言われる夏休み、ちょっと緊張気味かもしれません。
都内の小学校では、明日7月20日(木)が終業式のところが多いようですが、6年生は夏期講習の日数が多いので、明日から数日間の使い方が重要になってきます。
■ ここから数日間の使い方が重要
たとえばサピックスの場合、6年生の夏期講習の日程は全部で18日。
5年生が全20日であるのに対して日数が少ないのですが、8月下旬に「夏期集中志望校錬成特訓」という演習講座があるので、これに出席すると全部で23日。
40日のうち23日を塾で取られる上、講習会期間中の休みは、講習会の復習や宿題でやりきれなかったものに充てる、というハメになりがちです。
また8月24日に「夏期集中志望校錬成特訓」が終わりますが、その数日後に8月のマンスリーテスト(このテストからはマンスリーテストも範囲がない実力テストになります)があり、その対策もしたいので、8月末も塾以外のことに使えるのは数日。
だから、学校の宿題の主なものや弱点補強などは、夏期講習が始まるまでの数日間にやっておきたいところなのです。
塾によってスケジュールやカリキュラムは違いますが、特に6年生はここから数日間の使い方が重要なのは同じです。
うまく時間を使ってください。
■ 「夏、あれだけがんばったのに…」とならないために
夏期講習のカリキュラム、大きく分けると次の2つのタイプがあります。
①これまで習った総復習を行うカリキュラム
②年間を通したカリキュラムを夏の間もどんどん薦めていくカリキュラム
①のタイプの塾が多勢で、代表的な大手塾は日能研、四谷大塚、早稲田アカデミー、浜学園などです。
②は少数派で、代表的なのは首都圏ならサピックス、関西では馬渕教室など。
①のように夏期講習で今までの総復習をする塾にお子さんを通わせている場合「夏期講習で今までわからなかったところをわかるようになってくれたらいい」と考えがちですが、ちょっと注意が必要です。
それは、復習とはいえふだんと進度が全く違うということです。
以前一度習った単元とはいえ、毎日のように違った単元の学習が続くと、お子さんたちは「とにかく問題を解いて答えを出す」という学習に陥ってしまいがちなのです。
こうなってしまうと、最悪の場合は「考えているようで実は当てはめているだけ」といった状態になってしまい、夏の終わりのテストの結果に「夏休みあれだけがんばったのに…」と愕然とする、といった事態にもなりかねないのです。
夏期講習の授業から帰ってきたら、宿題にとりかかる前に「その日習ったことをしっかりと思い出す」という時間をとるようアドバイスしてあげてください。
■ 学校の宿題の「大物」はうまくこなそう
学校の夏休みの宿題、これはもう学校によって、担任の先生によって量も質も様々。
しかし、夏休みが始まって数日であらかた片付けてしまうのが理想です。
中でもお子さんたち、いや親御さんたちも頭を悩ませる「大物」が、読書感想文と自由研究ではないでしょうか。
「読書感想文は、本を読むまではいいんだけど、いざ書こうとすると何を書けばいいかがわからない・・・。」
「自由研究は、何をどのように研究すればいいのか・・・。」
いずれも、そんなことを考えている時間が最も長いお子さんが多いのです。
忙しい受験生、テキパキと片付けてしまいましょう。
主任相談員を務めさせていただいている「中学受験情報局 かしこい塾の使い方」でご一緒している小川大介先生、辻義夫先生のコラムに、いいヒントがあります。
ぜひ参考にしてみてください。
夏休みの宿題~読書感想文を簡単に書くコツ~
理科の成績が上がる自由研究
いい夏にしましょう!
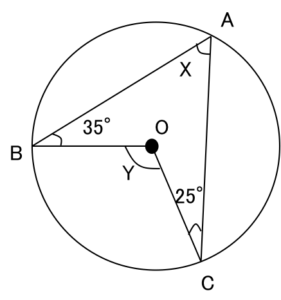
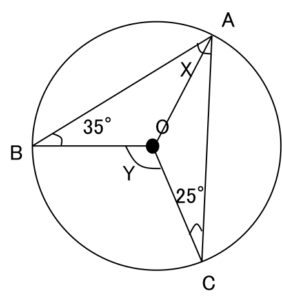
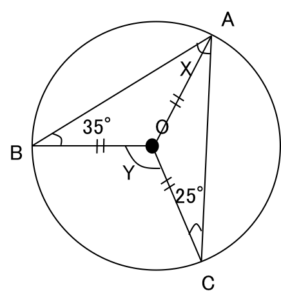
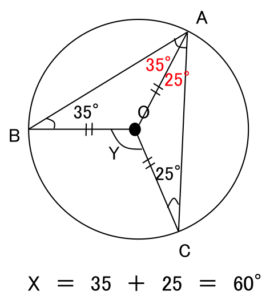

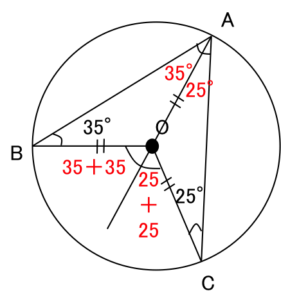
■2月18日(土)、秋葉原にてセミナーを行いました。
日経BP社「中学受験 基本のキ!」共著者の小川大介さんと講師を務めさせていただいた、日経DUALさん主催のセミナーだったのですが、いろんな発見がありました。
あらかじめどんな話をしようかと、できるだけ綿密に打合せをするのですが、いざ現場で話すと、さらにどんどんお伝えしたいことが増えていきます。だからついつい2時間の時間内に収まりづらくなっていくのです(笑)。
こんなに伝えたいことがあるなら、あらかじめもっと段取り良く話の構成を組んだのに、と我ながら反省するのですが、そんなことから気づいたことがあります。
■「伝えること」と「伝わること」は違う
私は家庭教師としてご家庭に伺い、お子さん、お父さん、お母さんと毎日話をするのですが、たくさん話をすればするほど、「これは言わなくてもわかっているだろう」という過信がなくなっていくということを感じます。それは相手の様子、状態がわかるからで、「このことはこのレベルまで、この言葉で伝えないと伝わらないぞ」と感じながら話すので、あれも、これも伝えたいという欲求というか、必要性が出てくるのです。
セミナーでは、塾に関してかなり突っ込んだことを話したのですが、塾の授業は「一方通行」になっている場合があります。講師が「伝えること」に夢中になりすぎて、受け取る側の都合、状態に目が配れなくなっているのです。授業の中でひとこと、ある言葉を端折っただけで、子どもはわからなくなるのです。いや、子どもだけではないですね。大人の目からはそういう状態の講師は「訳の分からないことを言っている人」と映るでしょう。
■端折らずに、具体的に伝える
親子の会話ではそこまでひどい状態は少ないかもしれませんが、でもついつい「端折る」ということをしてしまいがちです。あまりにも近い存在なので「これくらいは伝えなくてもわかっているだろう」と考えてしまった経験は、私にも多々あります。
今日のセミナーでは、一週間のスケジュールを立てるにも、志望校を決めるにも、お子さんとしっかり、時間をとって話をしましょうという話をしたのですが、話をすればするほどスケジュールは実行可能なものに近づいていきます。親のフラストレーションが溜まる原因は、実はお子さんのせいではなく、お子さんに伝えていないのに「やってくれるはず」と感じるところにあります。
親子だけでなく、夫婦でも友人でも、具体的に伝えるというのは大切で、とても効果があることです。
他人同士だとできることが、とても親しい存在の、本当に大切な人相手だと、ついつい相手に甘えてできなくなる。
家族ですからそういう優しさも心地よいものですが、ちょっと意識して「具体的に伝える」ということを実行すると、ちょっと生活が変わるかもしれませんね。