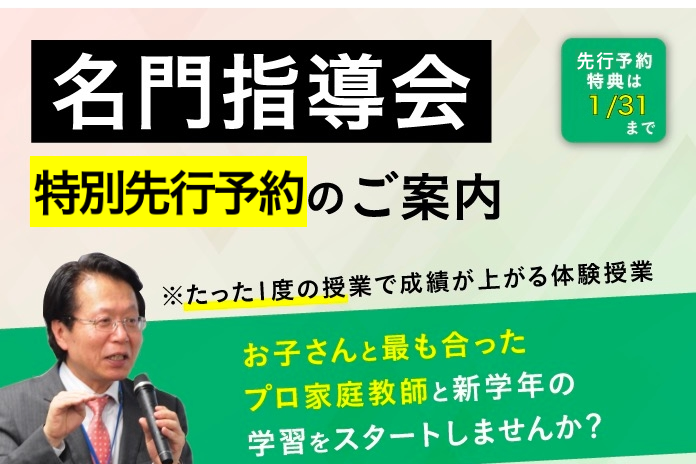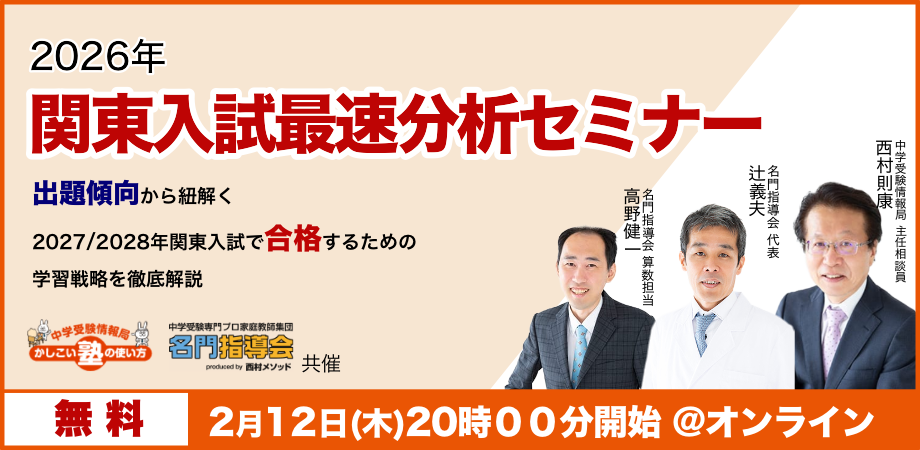カテゴリー: 小5向けアドバイス Page 6 of 10
8月最後の1週間です。
■秋から5年生が直面するテストとは
■「実力がない」というより「応用力がない」
■「考える」勉強をしているか
■家庭内ミニ授業で「考える勉強」を
今回は、困っている子供たちの気持ちつまりマインドに注目してみます。
成績が停滞している子供たちの多くは、学習すべき内容を整理してあげると
どんどんと成績を上げていきます。
ところが、それだけでは全く効果が無い子供が常に一定の割合で存在します。
それは、子供の気持ちでが原因です。そして子供の学習に向かう意欲を妨げるマインドの
原因を作っているのは、子供本人では無く周りであることが多いのです。
1 やらされ感一杯の嫌々学習
家に帰ってくれば、「早く勉強をしなさい!」。
学校の勉強が終わったと思ったら、「早く塾の勉強をしなさい!」。
塾の勉強をしていると、「いつまで計算をやっているの、そんなにだらだらやっていると、
文章題ができないでしょ。それに、社会や理科の暗記はどうするの。
それに、国語の宿題もあるでしょ!」
このようなお母さんの台詞が日常化することが、こどもの「やらされ感」を高めてしまいます。
これをやっても、その後あれもやらないといけないし、それが終わってもあれもやらないと、・・・・。
永久に終わらないような呆然とした気持ちになってしまいます。
・あれもこれも一度に話さない。今やるべきことを最大2つだけに絞って話す。
そして1つが終わったら、「頑張ったね。」と認めて労ってあげる。
2 親子喧嘩
お子さんのいい加減さを見つけたときに、ここぞとばかりに攻め立てていませんか。
「何この片付け方は!このプリンとはこっちに仕舞うように言ったでしょ。
この前もそうだったでしょ。
いつもいつもそうなんだから。
そんなことをやっているから、成績が上がらないんでしょ。
お母さんが見張っていないとちゃんとできないの!
この前もそうだったでしょ。
目を離したすきに、プリンとを引き出しに突っ込んだでしょ。
そんなずるい事をやってて良いと思っているの!・・・・・」
・叱ったりたしなめたりするときは短く、そして威厳を持って。
過去の話を持ち出して長々と説教を続けるのは最悪です。
30秒を越える説教の内容は聞いていません。
そして長くなればなるほど、内容よりもお母さんの苛立ちや怒りだけを感じとるようになります。
それがお母さんへの反抗心のもとになります。
また、お母さんの説教や激怒ですら、首をすくめて時間が経つのを待っていればよいことを
学習してしまいます。
そうなると、お母さんとしてはより強い言葉、より子供の気持ちにぐさりと突き刺さる言葉を
使わざるをえなくなってしまいます。
そのうちに、「うるさい!くそばばー!」という信じられない反撃を食らうことは、
珍しいことではありません。
3 こどもの自己肯定感をどんどん壊してしまう台詞
「なぜ、こんなのが分からないの!」
「この前もやったのに、もう忘れたの!なぜ、そんなに早く忘れるの!」
こんな台詞を使う塾の講師や家庭教師は、子供を教えるべきではないと思っています。
そんな簡単なことをなぜ納得させられなかったのか、
なぜそんなに早く忘れてしまうような理解しか与えることができなかったのか。
自己反省の材料にすべきことを、子供への責任転嫁をしているわけですから。
そして、親御さんもこのような言葉を使わないでほしいのです。
このような言葉を、ダブルバインドといいます。
「なぜ、こんなのがわからないのか」と聞かれて、
「あまりよく聞いていなかったから。」と言えば叱られて、
「頭がよくないから」と言えば、「言い訳ばかりをして」と叱られます。
どのような返答をしても、責められることがわかっている質問を、ダブルバインドの質問と言います。
このような質問を投げ掛けられた子供は、反抗心を沈殿させながら、鈍感の鎧を身に付けるしか、
なすすべがありません。
中学受験の過程で、家族のコミュニケーションが深まりお互いを信頼しあえるようになることが
最良です。
ところが、中学受験のために親子げんかが増え、関係がぎくしゃくしてしまっている例を
無数に見てきました。
親子関係が子供のマインドを決定してしています。和やかな明るい親子関係を心がけてください。
今回は、「小5小4で成績が中位、そして上がらずに困っている人」のついて、学習内容を書いて行きます。
家庭学習の優先順位は、普通
1 宿題
2 授業の復習
3 暗記
であることが多いのですが、これが実は間違いなのです。
理想は、
1 授業の復習
2 暗記
3 宿題
です。
復習主義の(今のほとんどの進学塾です)塾の宿題は、授業中にやった問題の類題が宿題に出ます。
授業が終わってまだあまり時間が経っていませんから、
「あの公式で解ける問題だ」とか、
「あれは割り算で解けた問題だ」
とかの記憶が鮮明です。
そのために、なぜその式を使うと答えになるのか、なぜ割り算なのかを理解しなくても、
正解が出てしまうことになります。
入試に向かう最終段階では、「問題を読んだ瞬間に使うべき公式が分かる」状態にする
必要があるのですが、そうなるためには問題パターンの本質をとらえる必要があります。
問題パターンの本質をとらえるには、「何が分かって」、「何を出す問題か」、
そしてその過程で「どんな考え方が必要なのか」を理解して、自分なりに分類していくことです。
この本質をとらえる時間を省略して、いくら類題演習を繰り返しても学力が向上しないのです。
近頃の御相談の大多数を占めるのは、
「頑張って勉強しているのに成績が上がらない」
「復習テストは出来るのに、総合テストになると点数が取れない」なのですが、
この原因が、本質を理解する事を省略しているからなのです。
塾の授業から帰ってきてすぐに、授業の再現をしてもらいたいのです。
原則は頭の中で行う作業です。
ノートとテキストを出して、問題文を読み、ノートの書き込みを見て、先生からどんな説明を聞き、
その時にどのように感じて、どのように納得をしたか、
これを思い返す時間が大切なのです。
これが授業の復習です。
始めは、お子さんを先生役に、親御様が生徒役になって、
「先生、この問題を教えて!」(親御様)
「エッヘン、それじゃあ良く聞いておくんだよ。これはね・・・・」(お子様)
このような場面を作っていただくのは、すごく効果的です。
ユーモアにあふれていますし和やかです。
このような数問の復習によって、理解の幹ができあがります。
その後に宿題をやって欲しいのです。
「こんなにたくさん宿題があるな!急がないと間に合わないぞ!早く終わらせなくっちゃ!
」このような心の動きが日常化してしまうことが一番危険な事なのです。
暗記を二番目に挙げました。これは理科や社会の学習についてです。
理科や社会の宿題は、ほとんど問題を解く事です。でも、問題を解く事は、
「必要な知識を覚えたかどうかの確認」にしか過ぎません。
特に小4小5段階では問題が単純な分、なおさらです。
まだ、覚えてもいないのに、確認をしても意味がありませんね。
必ず、覚えてから確認をするように学習の順序を修正してください。
そして、覚える前に、説明部分をしっかりと読む事も忘れずに実行して欲しいのです。
重要語句だけの暗記は、知識の離れ小島を増やすだけで、本格的な問題には対応できません。
文脈の中で理解して覚えた知識がテストで使える知識になります。
細かく見ていけば、お子さん一人一人、修正すべき箇所は異なります。
でも、上記の2つに注目していただくだけでも大きな効果がありますのでお試しください。