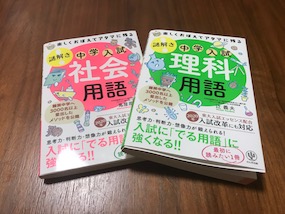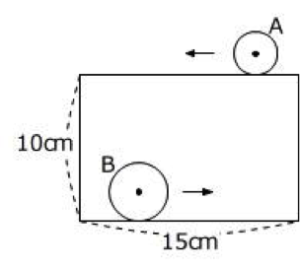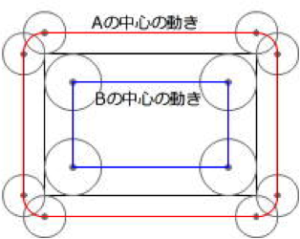みなさんあけましておめでとうございます。
受験生はいよいよですね。
■「前受け校」も真剣勝負
関西の受験生は、この週末が大阪・兵庫の入試日。
いわゆる「前受け校」が岡山の岡山中学校、岡山白陵中学校の場合、もう試験がありましたね。
四国の土佐塾中学校、北海道の函館ラ・サール中学校の県外入試も1月8日(月・祝)に行われたばかり。
いよいよ13日の入試に向けて、関西の受験生の皆さんは最後の追い込み、という状態ですね。
一方、首都圏は2月1日が東京、神奈川の統一入試解禁日ですが、今から1月下旬くらいの期間に千葉県、埼玉県の学校の入試日が集中しています。
前受け校に関しては、
・練習のつもりで受け、進学する予定はない
・受験結果によっては進学を検討する
などいろんな考え方で受験するご家庭があると思いますが、ぜひとも色んな面で受験から多くのものを得てほしいですね。
「前受け」と呼んでいるとはいえ、生半可な気持ちで受験に臨んでいる受験生はいないはずです。
受けるからには「合格」の2文字を得たいと思います。
どんな学校の入試でもそうですが、真剣勝負です。
中学校側から「うちに入学してください」というオファーがもらえるかどうか、という大切なプレゼンの場です。
入試の雰囲気、厳しさ、その他いろんなことを感じると思います。
もちろん合否という結果もそうです。
入試ですから、合格という結果もあれば不合格という結果もあります。
多くの場合、前受け校として選ぶのは「順当にいけば合格という結果を得られる可能性が高い学校」だと思います。
そんな受験でも、当日緊張して力が出しきれなかった、といった理由で不合格という結果になることもあります。
そんな結果の受け止め方として、少しお話しします。
■「前受け校」の合否の受け止め方
合格だった場合、ひとまずは「ひと安心」です。
このときあまり子どもを舞い上がらせず、「よし、この調子で第一志望校も受験しようね。当日の試験でポイントだったのはどんなことだったと思う?」と「勝因」を思い出させてあげてください。
それは「落ち着いて受験できた」かもしれないし「思ったより(思った通り)問題が易しかった」かもしれません。
勝因がどんなことだったとしても、その中から第一志望校の受験に活かせることは見つかるはずです。
「落ち着いて受験できた」のが勝因だったら、「●●中学校の受験生たちも、あなたと同じくらいの実力の子たちだから、焦らず落ち着いて問題に集中すれば良さそうね。」といった具合です。
さて、前受け校で不合格だった場合はどうでしょう。
第一志望校の受験日までに「気持ちのたて直し」が必要となる場合もあります。
「失敗したのが前受校でよかった」と一度気持ちに区切りをつけさせ、前を向かせるのもひとつの方法です。
前受け校として選んだ中学校の方には悪いのですが、本来は第一志望校に合格したかったのだから、と気持ちを前に向かせるのです。
わずか11才、12才の子どもの受験、大人以上に気持ちが結果に現れるものです。
これまででいちばん、お父さん、お母さんの支え、言葉がお子さんにとってありがたい数日、数週間になります。
親子でしっかり乗り切っていきましょう!