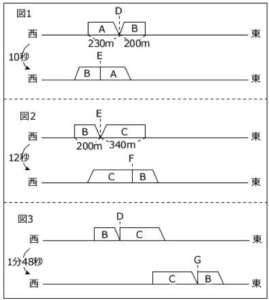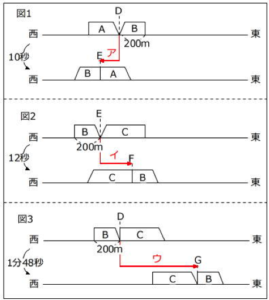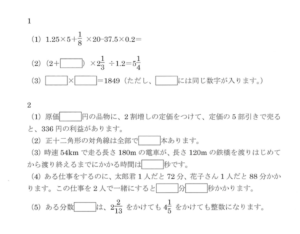■学年終盤のテストに向けて
11月、6年生はいよいよ直前期、過去問の演習に励む時期です。
5年生までのお子さんは、来年度に向けて準備をしていきたいですね。
5年生は受験学年である6年生を控え、来年の塾のクラスを決めるテストへの対策を立てていきたいところです。
サピックスのお子さんは、1月に「新学年組分けテスト」があります。
四谷大塚は毎月の「公開・組分けテスト」、日能研は公開模試が新学年のクラスを決めるテストになりますね。
さて、それらのテストに備えてですが、過去のマンスリーテスト、カリキュラムテスト、週テストなどのなおしを始めることをおすすめします。
マンスリーやカリテはいわゆる「復習テスト」で、実施された時点では「習ったばかりの単元」ですが、 時間がたってから改めて取り組んでみると、よい復習の題材になりそうです。
気になっている単元、春先に習ってしばらく取り組んでいない単元を1つでも、2つでも「つぶす」ことができれば、ここから学年がわりまでのテストで数点、得点の上乗せができるはず。
まずは動き出してみましょう。
■4年生は理社の勉強法の確認を
理社に関しては、4年生、5年生のお子さんの多くは「覚えることが中心の科目」と思っています。
確かに、特に4年生は理科でも暗記分野が中心で、あまり複雑な計算問題はでてきません。
毎回の宿題をきちんとやって重要事項を覚えていれば、マンズリーやカリテ、四谷の週テストなどでは点を取れるでしょう。
ただし、毎回「覚える→テスト」のサイクルを繰り返すだけでは、実力テストで点が取れなくなってきます。
5年生のお子さんの中には、もうそれを実感している子も多いかもしれません。
範囲が無いテストになると急に成績が下がるなら、勉強法を見直すべきです。
ふだん学習している単元の1つ1つは覚えているけれど、それらに有機的なつながりがないと、実力テストでは成績が上がりません。
では、お子さんの知識に「有機的なつながり」があるかどうかをどうやって確かめ、そのつながりをどうやって作っていけばいいか。
1つのおすすめは、マインドマップです。
たとえば「二酸化炭素」という言葉からどれだけのことを連想できるか、お子さんに思いつくままに書き出してもらうのです。
お子さんによって様々でしょうが、「光合成の原料の1つ」という知識が真っ先に出てくるお子さんもいるでしょう。
では、もう一つの原料は何だったかというと、根からすいあげた水ですね。その水が通る管が道管で、光合成でできた養分を運ぶのが師管で・・・」と枝葉が広がっていきます。
一方、別の太枝として「二酸化炭素の製法は石灰石を塩酸と反応させる」という知識が出てきます。
「石灰石主成分は炭酸カルシウムで、これは石灰水に息を吹き込んだときにできる白い濁りと同じもので・・・」と枝が広がっていきます。
この枝葉の広がりこそ、お子さんの知識の網。
どれくらい広げられるか、お父さん、お母さんも参加して書き出してみる。
たまにそんなことをしておくと、実力テストで使える知識ができていきます。
書き出さないまでも、食卓でこんな話題が持ち出せればずいぶん「机の上以外の勉強」になるものです。
ぜひ試してみてください。