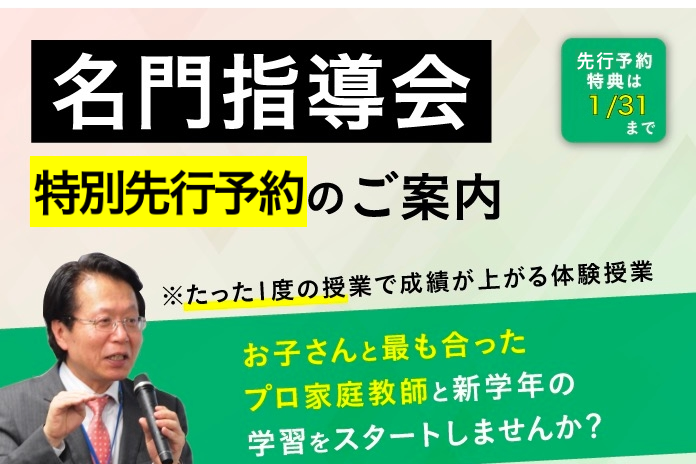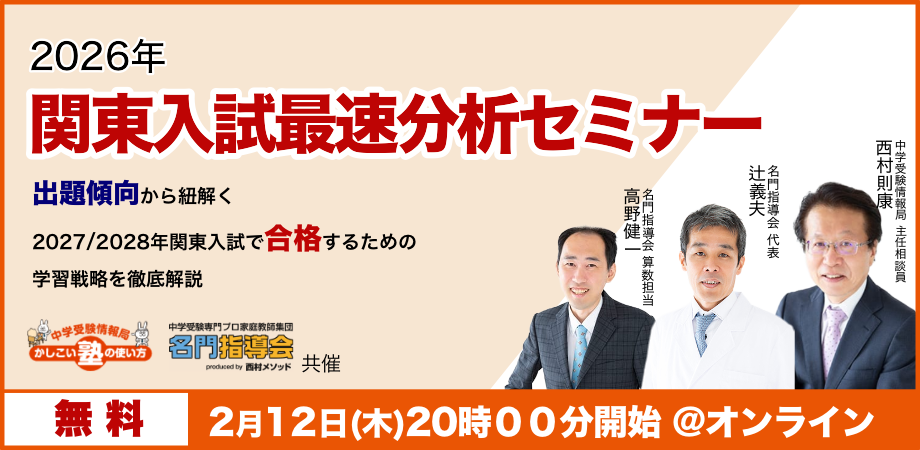□夏休み後の小6組分けテスト□
サピックスでも、四谷大塚でも既に組み分けテストが実施されました。
夏の学習の成果は現れていますでしょうか。
■あんなに頑張ったのに、点数があがっていない■
実はこのようなお子さんが多いのです。
夏休みの学習は、体調や気力を考慮して、日々の学習を微調整して行くことが大切です。今年のように暑過ぎる夏はなおさらでした。
夏に、あんなに学習を頑張ったのに点数が上がっていない理由の多くは、テスト当日のコンディション調節の失敗です。
下記の内容をチェックしてみてください。
□前日はしっかりと睡眠時間をとった。
□夏期講習の後半は、どっしりと落ち着いて学習出来た。
(あたふたした学習から抜け出せた)
□テストの数日前から、問題文をしっかりとよむ練習を取り入れた。
□テストの数日前から、丁寧な字で計算をする練習を取り入れた。
いかがでしょう。
各塾共に、夏期講習では、多量の問題をスピーディーに解く練習を重ねてきました。
パターンの確認に重きをおいた学習だったはずです。
早稲田アカデミーや日能研、四谷大塚(Sコース以外)は、テキストの構成もそのようになっています。
これが落とし穴です。
一方、今回の組み分けテストは、例年どおり入学試験を意識した文章の長い問題や、パターンから少し外した問題が多かったのです。
問題をながめた瞬間に、頭の引き出しからその問題の解き方を探し出して、素早く解くという条件反射的な学習をしてきたのに、実際の組み分け問題は、問題文
を丁寧に読んで、わかっていることは何か(条件整理)・聞かれている事は何か、の2点を正確に捉えて解く問題が多かったという事になります。
まず、テストの問題用紙に残った計算のあとや、メモ書きをしっかりと見てあげてください。
「あっ、こんな引き算をまちがっている」とか「こんな雑な考え方をしている」、また「あんなに学習をした事をちゃんと思い出せていない」というような事に気付かれるはずです。それを今後の学習に生かしていただきたいのです。
こんなミスをして!と叱るのではなくて、
「もっと丁寧な数字で計算をしていればどうだったと思う?」
「後5秒でもいいから、思い出す努力をしていたらどうだったと思う?」
というように、お子様自信が改善すべき点に気付くように話しかけてあげて欲しいのです。
そして、
「夏がんばったのに、思ったような点数がとれない子って多いんだって。そこで諦めずに、欠点を修正出来た子は必ず次のテストで、夏の頑張りの成果が出るそうよ。」と言ってあげて下さい。
これは、長年生徒の指導をやってきた私の実感です。
あと、数週間で四谷大塚の合不合判定テストやサピックスの合否判定テストがあります。
それにむけて、今から心身のコンディション調節をはじめてあげてください。