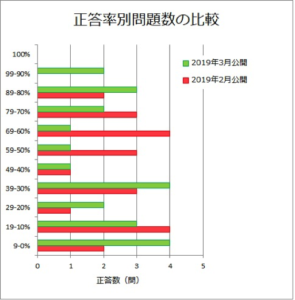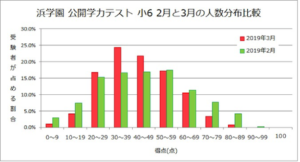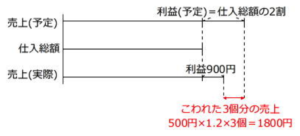皆さん、こんにちは。
塾ソムリエ西村が主催する名門指導会において、関西エリア統括を担当している都関です。

西村のコラムページの場を借りて、関西の情報をお伝えしています。
■大学入試改革と中学受験人気
皆さんもご存じのように、現行の「センター試験」は2020年1月の実施を最後に廃止され、2021年1月からは「大学入学共通テスト」に変更されます。
この「大学入試共通テスト」と「センター試験」との大きな違いは、記述式問題の導入と英語の4技能(読む・聞く・話す・書く)評価の2点です。
しかし、育児・教育ジャーナリストのおおたとしまさ氏は「記述問題に関する課題は山積みで、教育現場からは不安の声も多い」ため、「大学入学共通テストを回避して従来通りの入試を続ける私大に人気が集まる可能性もある」(東洋経済オンライン4月23日)と言います。
そのような現況をうけてでしょうか、関西圏の2019年度の中学入試は、2018年度よりも延べ応募者数で約4%、統一入試解禁日の1月19日午前の応募者数でも約4.5%の増加となりましたし、近年の傾向として有名大学の付属校や系列校の受験者数が増えていましたが、今年度もこの流れに変わりはありませんでした。

■女子に人気があった進学校は…?
上記のような有名大学の付属校や系列校だけでなく、灘中や四天王寺中をはじめとする進学実績に定評のある中学も、2月のコラムでお届けしたようにあいかわらずの人気でしたが、中でも最難関の洛南高等学校附属中、共学化3年目の高槻中は、女子の受験者数が10%以上の増加となり、また応募者数は2018年度と変化がなかったものの西大和学園中の女子の実質倍率は5.9倍となりました。

これらの中学の入学試験における点数を見てみると、洛南高等学校附属中は、女子の併願の合格最低点が男子と同じ255点(400点満点)、専願では男子の201点に対して240点と非常に高いレベルの競争になっています。
高槻中でも、A日程(3・4科)の女子の受験者平均が算数60.5点(120点満点)、国語84.8点(120点満点)、理科58.9点(80点満点)、社会59.5点(80点満点)、合計262.3点(400点満点)であるのに対し、女子の合格者平均は算数75.3点(受験者平均プラス14.8点)、国語91.3点(同6.5点)、理科64.3点(同5.4点)、社会65.0点(同5.5点)で、合格者の合計点が受験者の合計点より32.9点高い295.2点という、こちらもハイレベルな争いとなりました。
※A日程では、4教科型の場合は、4教科の合計点、算数・国語・理科の合計点を1.25倍した点数、算数・国語・社会の合計点を1.25倍した点数の3つのうち、最も高いものが受験者の成績、3教科型の場合は、算数・国語・理科の合計点を1.25倍した点数が受験者の成績として算出されます。
B日程(3科)でも、女子の受験者平均が算数61.0点(120点満点)、国語90.1点(120点満点)、理科52.8点(80点満点)、合計203.8点(320点満点)に対し、女子の合格者平均は算数82.3点(受験者平均プラス21.3点)、国語100.1点(同10.0点)、理科60.4点(同7.6点)、合計242.8点(同39.0点)でした。
■人気共学校を受験する女子にとってのポイント
この高槻中の入試結果で注目したい点は、算数の合格者平均と受験者平均の差が合計点の合格者平均と受験者平均の差に対して、A日程で約45%、B日程で約55%と、算数で大きく点差が開く結果となっていることです。
また、2018年度のデータではありますが、西大和学園中の女子の場合でも、算数の受験者平均が71.5点(150点満点)で合格者平均は96.1点、合計点の受験者平均が278.2点(500点満点)で合格者平均は339.1点でしたから、算数の合格者平均と受験者平均の差が合計点の合格者平均と受験者平均の差に占める割合は約40%(国語は約23%)となり、やはり算数でどのように得点していくかが合否に大きく影響していると言えるでしょう。
浜学園や馬渕教室などの大手進学塾では、夏期講習の前後から志望校別特訓が本格化しますから、もし算数が苦手であれば、その前に不得意な分野を克服して、夏期講習や志望校別特訓をより効果的に活かせるようにしておくことが、洛南高等学校附属中や西大和学園中、高槻中などの人気共学校を志望する女子にとっては大切なことだと思います。