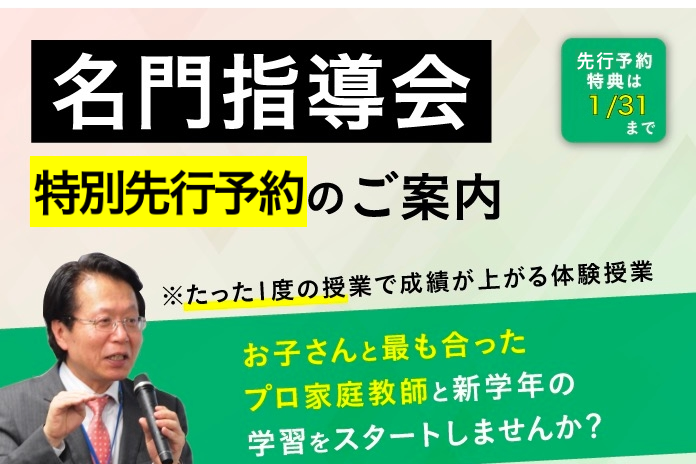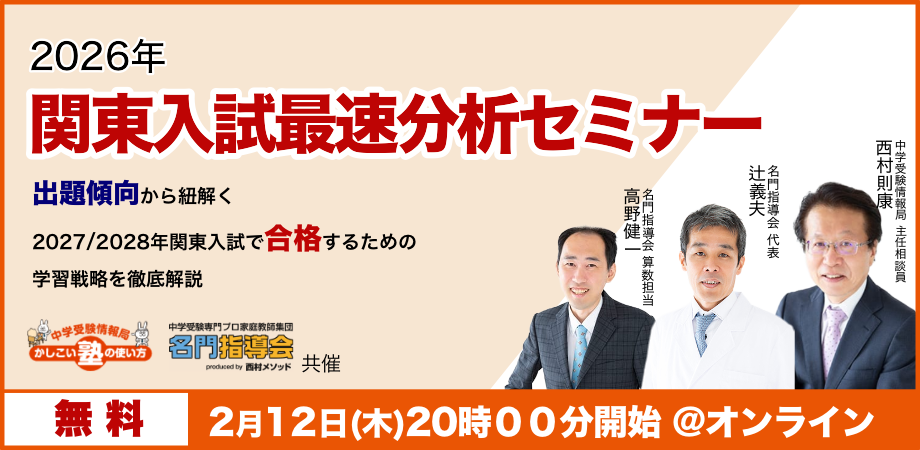なかなか宿題に取りかからないわが子を見て、あるいは勉強をイヤイヤやっている姿を見て、「もう、それなら受験なんてやめちゃいなさい!」なんてことを言ってしまったというお話を、初めてご相談に来られたお母さんから聞くことがあります。
ご家庭により様々ですが、中学受験をすることに決めた発端は、お子さん自身であることも多いようです。
特に男の子は、純粋というか気まぐれというか、ほんのちょっとしたことがきっかけで「僕◯◯中学校に行く!」と盛り上がったりするわけです。
それが悪いというわけではありません。男の子の親御さんならよく分かるのではないかと思うのですが、小学生の男の子というのはそんなものです。
■「自分で決めたんだから、やりなさい!」ではなんともならない
「それにしたって、自分で受験するって決めたんだから、さっさとやんなさいよ!」
お母さんがそんな気持ちになるのもわかります。「僕◯◯中学校に行く!」で始まった受験、だったらと協力し始めたお父さん、お母さんの心配をよそに、さっぱりテンションの上がらない様子を見せることがあるのも子どもです。
特に、6年生になってから受験することを決めて塾に通いはじめたお子さんは、塾の授業についていくのが大変で「やってもやっても結果が出ない・・・」という気持ちになりがちです。そのためテンションが上がらないことも多いようです。
中学受験の進学塾は、4年生、遅くとも5年生くらいには受験勉強を始めるものとしてカリキュラムを組んでいます。塾での5年生の「ベース」がない状態での6年生の勉強は、想像以上に大変なのです。さらに4年生のぶんまで抜けているとなれば、かなり地頭のいいお子さんでもずいぶん苦戦するはずです。
勉強のテンションが上がらないのがこのような理由だったら、「自分で決めたんだからやんなさい」では解決しません。
・志望校の偏差値と今のお子さんの偏差値にはどれくらいギャップがあるか
・塾の授業スタイルはお子さんの理解のスピード、レベルにあっているか
の2点をチェックしてみて、著しく無理がありそうなら志望校の変更、塾の課題量の調整や、場合によっては転塾の検討もしなければなりません。
■うまくいっているのにテンションが上がらない事例は少ない
塾の授業もよくわかって、成績も取れているのにテンションが上がらない、という事例はあまりありません。塾の授業がわかれば面白いですし、成績が取れれば嬉しいでしょうから、珍しい事例といえます。
このような場合は勉強面での問題というよりは、塾の友達とうまくいっていないなど、人間関係のトラブルなどが原因になっていることが多いようです。
やはり家庭学習のテンションが上がらない場合は、勉強面で何かの問題点を抱えていることがほとんどで、その原因を突き止めて解決することが大切です。
お母さんが感情的にならずに現状を把握するには「なぜ?」という質問ではなく「何?」という質問を心がけるのがよいでしょう。
「どうして宿題をやらないの?」
という質問はどうしても感情が先に立ってしまうし、お子さんもそう受け取りがちです。
感情でぶつかり合っても(ときには必要かもしれませんが)、お互い摺り減るばかりです。
「何があったの?」
という質問で、事実として何が起こっているのかを冷静に聞くようにしたいものです。冷静に聞いてみると、予想もしなかった事実がわかってきたりもするものです。
夏休みが終わり、日も短く忙しい毎日が戻ってきました。
目標を共有し、しっかりコミュニケーションをとりつつ2学期を乗り切っていきましょう。