もう10月です。
先月は3日にサピックスの5年生向けの「志望校診断サピックスオープン」がありました。
かなり難しいテストでしたが、また11月にもありますから、算数のテストをちょっと振り返っておきましょう。
全体の構成としては、
1.計算
2.小問集合
3.平面・立体図形
4.和と差に関する問題
5.数についての問題
6.速さ
7.図形・調べる問題
となっていて、非常に難度の高い問題です。
■点を取るべき部分は
サピックスオープンはA問題(処理力を問う問題)とB問題(思考力を問う問題)からなっていて、1〜4がA問題、5〜7がB問題という割り当てになっています。
もちろんすべてできればいいのですが、今5年生の子がこのテストを解くとき、点を取らねばならない部分は(今の学力状況にもよりますが)決まってきます。
もちろん思考力もつけておきたいのですが、まずは1〜4です。
「処理力を問う問題」とはいえ、思考力がなければ解けない問題ばかりだからです。
たとえば大問1の(3)は計算問題ですが
160L ÷ 2m2 = ( )cm
という問題。
なぜ計算問題の数値に単位がついているのかを考えないと、計算できません。
(もちろん160÷2=80は正解ではありません)
「体積を面積で割るということはどういうことか」を考えなければならないのです。
体積は 「底面積 × 高さ」で計算できますから、体積を面積で割ると立体の高さが出るのですね。
つまり160Lを160000cm3、2m2を20000cm2と換算すると、
「底面積20000cm2、体積160000cm3の立体の高さは160000÷20000=8cm」
と答えが出せるわけです。
■手を動かすことができているか
大問2の(5)は「3行問題」と呼ばれる小問です。
「はじめ、姉は妹より400円多く持っていました。姉は母から600円もらい、妹は500円使ったところ、姉の所持金は妹の所持金の3倍になりました。はじめ、姉は( )円持っていました。」
割合の問題ですが、線分図を書かないと解けませんね。

こう書いて初めて「③と①の差の②はいくらか」が見えてくるわけです。
こういった部分で取りこぼしがあると、いくら後半のB問題を頑張ってもなかなか点にはなりません。
サピックスに限らずですが、6年生に備えて5年生は「図や考え方などを書く」ということを徹底してみてください。
■11月の第2回志望校診断サピックスオープンに向けて
9月オープンの大問2から、(1)と(2)をご紹介しましょう。
(1)70を割ると6余る整数は、全部で( )個あります。
(2)まわりの長さが48cmで、たての長さが横の長さよりも6cm長い長方形の面積は( )cm2です。
・・・どちらも難しくはない問題ですが、(1)は「70を割る」であって「70で割る」ではないところ(1次違いで大違いですね)、(2)は「まわりの長さ」が48cmなのであって、「たて+横」は24cmであることに注意しなければなりません。
「そんなのに引っかからないよ」と思うかもしれませんが、いざテストになると何が起こるかわかりません。
「易しそうに見えても、どこかにひっかけがあるかもしれないぞ」
という意識で取り組みましょう。
「また、A問題を中心にとり、後半のB問題は(1)だけをうまくとる」
といったテストを受けるにおいての「戦略」を持つことも大切です。
11月に向け、普段の勉強から意識してみてください。


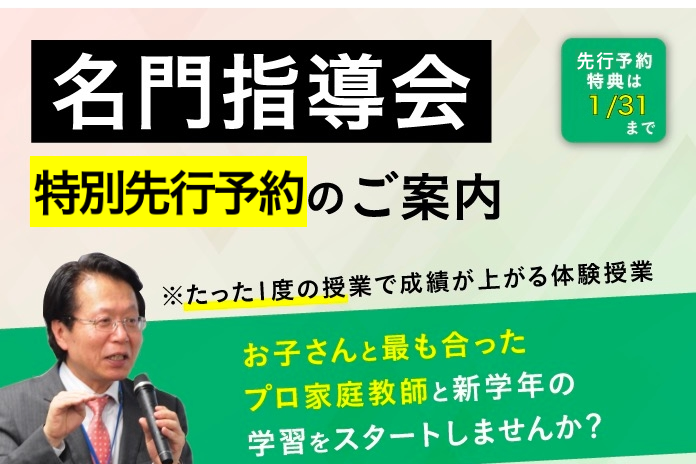
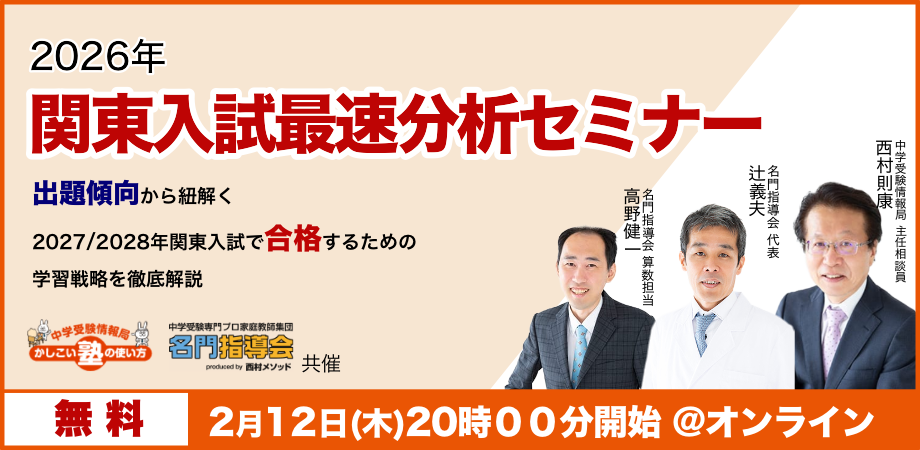




























コメントを残す